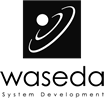会社を知る
製品・サービス
製品づくりのコンセプト
博物館専業として学芸員と膝を突き合わせるのが日常である私たちは、博物館ITにまつわるご相談のほか、さまざまな内容のお困りごとをうかがいます。
商品が情報システムである性格上、館運営のかなり深い部分までお聞かせいただくことも少なくありません。
中にはITの分野を逸脱するご相談も少なくありませんが、当社は可能な限り、解決への道筋をご一緒に考えます。
机上の空論ではなく、自社の都合でもなく、学芸員が現実に直面する課題を解決すること。
これこそが当社の事業の根本であり、「それは本当に博物館のためになるのか」という視点を製品・サービスづくりの判断軸に置いています。
その不変の姿勢は、当社のお客様方に向けて約20年・200回以上も実施しているインタビュー記事でもご確認いただけます。
現在は提供製品もクラウドサービスが中心となり、最近ではリモートによる会議の機会も増えましたが、そんな姿勢から、当社はそれでも可能な限り対面での打ち合わせを大切にしています。
ご相談やご依頼ごとへの対応だけでなく、新たな機能やサービスを着想した際には、こちらから学芸員に相談することも。
手間や労力を厭わず、言葉に加えてその場の空気や熱量まで感じ取るために全国各地を走り回る姿勢は、30年以上の時を重ねる中で当社のスタイルとして完全に定着しています。
I.B.MUSEUM® SaaS

現在の当社の主力サービスへと成長したクラウド型の収蔵品管理システムです。
収蔵品情報のデータベース、デジタルアーカイブシステムとしての役割を果たしつつ、展覧会の企画や他館への貸出など多様な業務で活躍。
さらに、学芸業務で蓄積したデータをそのまま活用可能なデジタルアーカイブ公開機能や、追加料金なしで音声ガイドサービスを実現できるスマートフォン・アプリなど、情報発信に関わる豊富な機能も実装しています。
2010年11月のサービス提供開始から順調に導入館を増やし続けており、現在では600館を越えるユーザを獲得。
これは、導入実績が数館〜数十館に留まるのが一般的な収蔵品管理システムでは、文字通り桁違いのトップシェアとなります。
ここまでの実績を確立できた背景には、「予算の壁」を前に立ち尽くす中小規模館にも無理なくご導入いただけるようほぼ限界まで抑えた料金設定もさることながら、開発当時で15年以上にわたり蓄積していた知見が生み出したデータ項目のアレンジ機能の存在があります。
歴史系・美術系・自然史系と館種によってまったく文化が異なり、所蔵資料の性質から館内文化、管理手法や項目体系、人員体制、運営事情まで「ふたつとして同じ施設はない」とされる博物館では、原則として同じシステムを複数の顧客でシェアするクラウドサービスは実現が難しいと考えられていました。
これに対し、現実的かつ豊富な項目体系のテンプレートと、それを自由に調整できるアレンジ機能を組み合わせることで「自館仕様のシステム」を作れるI.B.MUSEUM SaaSは、まさに業界全体の課題を解決。
しかも、その構築には数百万〜数千万円の予算が必要となっていた収蔵品管理システムを月額3万円のみで導入できることから、それまでシステムに手が届かなかった多数の中小規模館が相次いで採用。
ゆっくりと、しかし着実に日本の博物館界全体へと浸透しつつあります。
I.B.MUSEUM®

I.B.MUSEUM SaaSの前身で、収蔵品管理システムのパッケージソフトです。
1992年の創業以来、数多くの博物館でご利用いただいてきました。
前述の通り、扱う対象の大半が「そこにしかない1点もの」である博物館は、業務の流れから目録を構成するデータ項目の体系まで、館ごとに何もかもが違います。
そのため、パッケージソフトをそのまま導入することはできず、その館の業務に合わせたカスタマイズが必須となっていました。
Windows95以前の時代に製品化されたI.B.MUSEUMは、そのクラウド版であるI.B.MUSEUM SaaSの登場以前からトップシェアを誇っていましたが、それはカスタマイズの過程で有用と判断した機能をパッケージにも反映するプロセスを反復し続けた歴史でもあります。
その結果、学芸業務を幅広くカバーできるソフトウェアへと進化し、現在のクラウドサービスにも活かされることになりました。
ちなみに、このカスタマイズ作業は、収蔵品管理システムの導入コストが高騰する原因のひとつともなっていました。
中小規模の博物館では、この予算を捻出できない施設が大半を占めていたため、博物館界はほかの業界と比較してもIT化で大きく遅れを取っていたのです。
I.B.MUSEUM SaaSの開発は、上記の訪問活動で学芸現場の苦悩を目の当たりにし続けていた者として「気軽に導入できる収蔵品管理システムを提供したい」「業界全体を覆う停滞の空気を一新したい」と考えたことが原動力となりました。
博物館向けアプリ

I.B.MUSEUM SaaSは、一般の収蔵品管理システムの範疇を超えるほどの多彩な機能を搭載しています。
その象徴的な例が、ユーザ館が追加料金なしで利用できる数種のスマートフォン・アプリです。
いずれもI.B.MUSEUM SaaS内に格納されたデータを来館者のスマホに配信できるアプリで、日常の学芸業務で蓄積し続ける資料情報などをそのまま流用することで、来館者向けコンテンツの新規制作が不要に。
I.B.MUSEUM SaaSは、こうした学芸業務の負担軽減を意図した機能群も大きな特徴となっています。
なお、これらのスマホアプリは、もうひとつ大きなソリューションを内包しています。
ユーザ館がアプリを利用する場合、すべての館が同じアプリで情報を配信することになりますが、アプリの利用者から見ると「たくさんのミュージアムでサービスを利用できるアプリ」ことにほかなりません。
たとえば、音声ガイドアプリ「ポケット学芸員」は、行く先々の館で別のアプリをインストールすることなく、ひとつのアプリで多様な館のガイドを利用可能に。
運営側にも利用者側にもメリットをもたらすこのアプリは、現在200館近い博物館で採用されています。