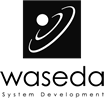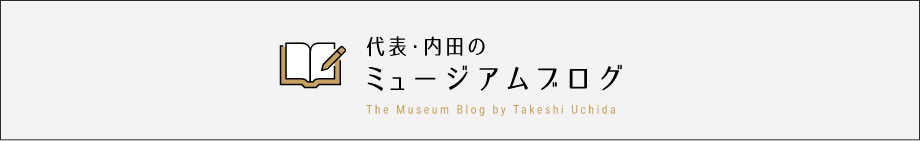2025.05.08
天才左官職人の鏝さばき! 漆喰鏝絵の世界 ~伊豆の長八美術館/国指定重要文化財 旧岩科学校
#現地訪問蔵などの壁の仕上げとして、左官職人が鏝(こて)と漆喰(しっくい)で作るレリーフを「鏝絵」と呼ぶのだそうですね。その漆喰鏝絵の世界に、かつて「神様」と呼ばれる天才職人がいました。彼の出生地である静岡県賀茂郡の松崎町で、その作品を集めたミュージアムの建設が決定すると、全国の職人たちが大集結したという左官界のレジェンド。そんなわけで、今回は「伊豆の長八」の世界に触れてきました。
「なかなか素敵な絵だなあ」と近づいて細部を見ると、とんでもないサプライズがあったのです。彫刻のような立体感と、極細ペンで描いたような緻密さ。その両方がひとつの絵の中に同居していて、はじめは「どういうこと?」とその場で混乱してしまいました。
左官の技術と絵師の画力が融合した、職人技の極み。この漆喰鏝絵を手がけた入江長八は、江戸末期の文化12年(1815年)に現在の静岡県賀茂郡松崎町で生まれました。12歳で左官職人に弟子入りした長八は19歳で江戸に移り、その才能を見事に開花。学んだ絵画と佐官 の技法を漆喰細工に応用するという離れ業で、名工「伊豆の長八」として大いに名を馳せました。
ここ松崎町の伊豆の長八美術館では、地元が輩出した天才職人の作品を150点ほど収蔵 しているとのこと。訪問前にホームページで知った超絶技巧を専門ミュージアムで目の当たりにできるということで楽しみにしていたのですが、建物の前で足が止まってしまいました。

昭和59年(1984年)にオープンした同館の建物は、建築家・石山修武氏の作品。「左官の神様」の殿堂ということで、建設工事では全国から延べ2,000人もの左官職人が集結したそうです。モダンなデザインと日本伝統の職人技術の共演は、人を強く引き付ける魅力がありますよね。
では、ほんのごく一部ですが、長八の漆喰鏝絵をご紹介します。

左が全体像、右はクローズアップです。「着物や手すりで立体感を出しているのかな」と感じて近づくと…もちろん、それどころではありませんでした。襟元の細かな柄も、髪の毛の1本1本も、すべて丁寧に描き込まれているのです。しかも、ペンや筆ではなく鏝を使うというのですから、予めそれを知っていても信じられないレベルです。

海の向こうに富士を望む、日本人にはお馴染みの構図。松崎町は、平成24年(2012年)に「世界でいちばん富士山がきれいに見える町」というエスプリの効いた宣言書を発表しています。近くに寄ってみると、やはり遠目には分からない職人芸が。細かな波しぶきは絵の技術、帆は漆喰の厚みで表現されています。2Dと3Dの一人二役、いや〜凄まじい鏝さばきですね!

松崎町内には国指定重要文化財「旧岩科学校」もあります。明治13年(1880年)に建てられたこちらの建物は、並べて貼った平瓦の継ぎ目に漆喰を盛り上げて塗る「なまこ壁」による純和風の佇まいに、バルコニーや窓など洋風のデザインを取り入れた和洋折衷が見事。長八の漆喰鏝絵は欄間にあり、多数の鶴が独特のタッチ描かれています。
とにかく圧巻なのですが、ふと「この引力をデジタルアーカイブで再現できるのか」という疑問が。細密な描写は高精細画像でなければ分からないでしょうし、漆喰の立体感はそれこそ3Dでしか伝わりそうにありません。両者を同時に体験するには、「超高精細3D」が必要かも? 令和最新のテクノロジーでも伝えるのが難しい江戸の技術とは、何ともロマンがあります。

左が伊豆の長八美術館、右が国指定重要文化財 旧岩科学校。美術館の手前に見える彫刻は、何とあのサグラダ・ファミリアの主任彫刻家として著名な外尾悦郎氏の手によるものなのだとか。帰り際、またまた足を止めてしげしげと観賞し、また写真を何枚も撮ってしまいました。
「日本で最も美しい村」連合に加盟する松崎町だけに、まだまだ魅力がありそうな気配。文化資源のデジタルアーカイブが待ち遠しいです。
伊豆の長八美術館 https://www.izu-matsuzaki.com/pages/69/
https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2016020300578/
重文 旧岩科学校 https://www.izu-matsuzaki.com/pages/54/
https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2016020300554/