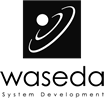- vol.228取材年月:2025年10月大妻女子大学博物館
公開できる情報から掲載することを習慣づければ
データベースは常に「新鮮な状態」を保つことができます。学芸員 青木 俊郎 さん
学芸員 髙塚 明恵 さん
 -歴史や民俗、考古、自然史まで総合博物館のように充実したコレクションをお持ちですね。手芸や履物のほか、瓦や骨格標本まで。
-歴史や民俗、考古、自然史まで総合博物館のように充実したコレクションをお持ちですね。手芸や履物のほか、瓦や骨格標本まで。
青木さん:軸となるのは大学史の関連資料なのですが、前身が大妻女子大学生活科学資料館ですので、まとまった染織のコレクションがあります。あとは、瓶細工とか。
-オブジェクトVRで見られるのですね。(作品を見ながら)凄まじいクオリティですね。瓶の中の細工を、瓶の外から作るのですか?
髙塚さん:はい、創立者の大妻コタカの教えを汲むもので、精神修養の側面もあったそうです。技法は大妻学院で継承されてきましたが、いまは途絶えてしまいました。
-それは残念ですね。ところで、お二方はいつごろ着任されたのですか?
青木さん:私は2020年です。当時は、Excelの目録はあったのですが、何台かのPCに散らばっていました。データベースの整備では、これらを頼りに、まず現物を確認する作業から入りました。
高塚さん:私は2022年なのですが、すでにI.B.MUSEUM SaaSが稼働していました。以前に勤めていた都内の自治体でも導入されていて、主に写真データの外部貸出手続きなどで利用していました。
-それは嬉しいです。こちらのデジタルアーカイブはしっかり公開されていますし、かなり完成に近づいている状態でしょうか。
青木さん:いえ、それが実はまだまだなんですよ。Excelのデータをすべて登録できているわけではないですし、分類はもっと整理したいですし…。
-え、ここまでできているのに、分類から見直されるのですか?
高塚さん:たとえば、ある寄贈資料の中に手芸や証書、手紙、写真などが混在する場合、当館では「どなたからの寄贈品か」「大学史に関係するか否か」といった視点で分類していまして。ただ、この方法では、形態が異なる資料を同じ大分類に登録しようとするとどうしても齟齬が出ますので、形態中心の分類への変更を考えています。
-かなり根本的な見直しになりますね。
高塚さん:そうですね。そもそもどのような大分類が適切なのか、収蔵資料の実態に即して検証しているところです。一方で、寄贈者ごとに検索できないと困りますし、館の性質上「大学史資料」か「それ以外」かという観点も重要ですので、全分類共通の項目を設定することで対応しています。
-なるほど。分類と項目を上手く設定すれば、情報の正確性と業務上の検索性を共存させることができるわけですね。
 -それでも、公開されているデータベース自体は、とても充実しているように見えます。
-それでも、公開されているデータベース自体は、とても充実しているように見えます。
髙塚さん:いま公開しているのは、手芸や瓦、靴、それに学校機関誌など、すでに分類が確定していて、これから情報の整理を実施したとしても影響を受けにくい、今後大分類の移動はない可能性が高い分野の資料が中心なんです。
-すべてが完璧に整うのを待つのではなく、可能なものから公開するという考え方でしょうか。
青木さん:仰る通りです。先ほどの寄贈品にしても、すべて展示できるのがずっと先になるとしたら、公開しやすい写真だけでも先に展示した方が、ご寄贈くださった方のお気持ちにお応えできますからね。内容が確認できた順に公開することを習慣づけると、内部的にも成果が見えやすいですし、途切れなく新しい情報を更新できることにもなります。
-なるほど、一括して公開できない事情を逆手にとって、新鮮味の演出にできるわけですね(メモ)。公開ページづくりでは、ほかの大学博物館の事例を参考にされたりしますか?
高塚さん:はい。たとえば、学校機関誌の公開ではブックページャーの機能を使っているのですが、これは東京家政大学博物館さんの「谷中リボン」の見本帳を参考にさせていただきました。
-設定方法などは難しくなかったですか?
高塚さん:そうですね、操作面で何度か躓きました。あれは詳しいマニュアルがあった方がよいかもしれませんね。
-お手数をおかけしまして申し訳ございません。東京家政大学博物館様と言えば、フッタ部分も上手にお使いですよね。
青木さん:(ページを示しながら)当館では、ここにデータベースの更新情報を掲載しているのですが…。
-更新情報そのものが資料へのリンクになっているのは、とてもよいアイデアだと思いました。まだ内部的に大仕事が残っているとは思えないクオリティですが、こうした作り込みと並行して項目の見直しも進めておられるのですか?
高塚さん:はい。たとえば「寸法」という項目でも、絵画と彫刻、染織では計測する場所が違いますので、まず分類体系を作って、そこから必要になる項目を検討しています。お陰様で、かなり固まってきたところです。
-これだけジャンルが多様ですから、項目の見直しだけでも大変ですよね。実作業は何人かで手分けしているのですか?
青木さん:学芸員は私たち二人なので、私が歴史、高塚が美術と民俗を中心に担当しています。
-お二人だけなのですか、大変な労力ですね。項目設定と言えば、システムのインターフェイスのリニューアルで設定方法が変わりましたが、お困りのことはありませんか?
高塚さん:今のところは大丈夫です。たとえば学校機関誌は、システムの初期設定で用意されている「逐次刊行物」をアレンジして作りましたので、この方法で何とかなりそうです。
-器用に使いこなしておられますね。いや、本当にすごいです。
 -項目体系の見直しがあるとは言え、資料情報はかなりの部分が登録されていますよね。
-項目体系の見直しがあるとは言え、資料情報はかなりの部分が登録されていますよね。
青木さん:いえ、登録できているデータは一部に過ぎません。データ登録の前に、まず実物を確認しなければならない資料が、あと数千点は残っています。
-それは大変ですね。しかもお二人での作業となると、気が遠くなりそうです。
青木さん:でも、学生たちが実習を兼ねて手伝ってくれますから。カリキュラムには資料整理のほか3D撮影なども含まれていて、延べ50人くらいで作業するんですよ。
-それはすごいですね。一般のミュージアムが羨みそうです(笑)。
青木さん:大学博物館が恵まれている点ですよね(笑)。学生にとっても母校の歴史に触れる機会になりますし、実習の成果は公開されますので、モチベーションも高く取り組んでくれていますよ。
-(画面を見ながら)3Dデータは、I.B.MUSEUM SaaSとは別にSkechfabでも公開されているのですね。公開は本当に充実していますが、館内でのシステム活用はいかがですか? クリップリストなどのサポート機能はご利用でしょうか。
高塚さん:業務でフル活用できているかと言えばまだまだですが、各機能は積極的に使っています。
-たとえば、どんな機能をお使いですか?
高塚さん:細かいところでは、借受管理で返却処理を行った後も作品情報を閲覧できる機能は意外に便利ですよね。特に資料利用に関係する機能や帳票の機能も、もっと活用していきたいですね。
-使いこなしていただいていますね。逆に、ご要望などはありませんか?
髙塚さん:展示に関して、キャプションづくりや解説文の管理もすべてシステム上で行いたいので、文字数をカウントしてくれる機能が欲しいですね。
青木さん:アノテーションを入れられる機能とか、先ほどの3Dデータならサムネイル画像の表示機能とか…。欲張りですみません(笑)。
-とんでもない、とてもありがたいです(メモ)。今後もお気付きの点があれば、お気軽にご指摘くださいね。本日はお忙しい中、勉強になる話をたくさんお聞かせいただき、本当にありがとうございました。
- Museum Profile
-
大妻女子大学博物館
「日本人のくらしの知と美」をテーマに、衣・食・住・学に関する充実の資料を収蔵。平成19年に資料館として設立され、平成24年に博物館に改称されました。明治41年に大妻コタカが創設した裁縫・手芸の私塾から発展した「大妻学院」関係資料を核に、創立者夫妻ゆかりの品々などを豊富に展示。博物館学芸員課程の実習受け入れを通じて後進の育成にも注力しつつ、地域の生涯学習の拠点としても重要な役割を担っています。
〒102-8357 東京都千代田区三番町12 図書館棟 地下1階
電話:03-5275-5739
ホームページ:https://www.museum.otsuma.ac.jp/