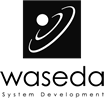- vol.227取材年月:2025年9月府中市美術館
デジタルアーカイブの公開を果たした今は、
これをどう活用できるのか、今からワクワクしています。学芸員 小林 真結 さん
 -小林さんはいつ頃こちらに赴任されたのですか。
-小林さんはいつ頃こちらに赴任されたのですか。
小林さん: 2012年に着任しました。当時は紙台帳と、内製で作ったファイルメーカーで作品データを管理していたのですが、数年に一度発行する紙の目録の方が主に使われていました。
-あの頃は多くの館で、紙の目録が使われていましたね。どの館でもかなり使い込まれていて、学芸員の皆さんは「あの作品はこの辺に載っている」と当たりをつけて、すぐに該当ページに辿り着くんですよね。あれはあれで、プロはすごいなあと思っていました(笑)。
小林さん:ただ、目録を作るまでのデータの整備は、アナログではやはり大変で。表記揺れや空欄がそのままになってしまうこともありましたしね。確か、2020年くらいまではそんな状態だったと思います。
-電車内の広告などでも展覧会の情報をお見かけしますが、企画展がとても活発なご様子ですし、なかなか時間も取れないですよね。
小林さん:はい、年に5本をほぼ自主企画で開催していますので、そちらにかなりリソースを取られます。
-そんな状況を考えると、システム導入から公開まで、かなり短時間で実現したことになりませんか?
小林さん:そうかも知れませんね。きっかけは、文化庁のアートプラットフォームへデータを提供したことなんです。作品リストをExcelでお渡しすることになったのですが、すぐに出せるデータがなくて、これは改善しないと…という話になりまして。
-なるほど、意外なきっかけですね。
小林さん:そうですね。ちょうどコロナ禍での事業の変更などもあり、ファイルメーカーのデータをもとに整備を進めたんです。
-その状態から、データ公開まで一気に進められたのですか。
小林さん:世の中全体で、美術館の作品データ公開についての需要が高まっていましたからね。それまでは、データベースは館内の作品管理に使うものという位置づけでしたが、市や美術館運営協議会などからデジタルアーカイブを推進すべきという声もあって、公開を見越したデータの整備を始めたんです。
-時代の要請ということですね。それにしても、お仕事が早くて驚きます。
 -システムのご検討から実際のご導入まで、少し時間が空きましたよね。この期間は、データを整備されていたのですか?
-システムのご検討から実際のご導入まで、少し時間が空きましたよね。この期間は、データを整備されていたのですか?
小林さん:はい、まずポジフィルムのデジタル化を行いました。それまでは画像が必要になるとその都度スキャンしていましたが、頻繁に行っていると劣化も心配ですから。
-なるほど。データを地道に整備していたことも、導入から公開までが短期間だった理由のひとつなのですね。データ移行は順調でしたか?
小林さん:はい、特に問題ありませんでした。ファイルメーカーの時点で独自の項目体系で管理してきましたので、I.B.MUSEUM SaaSの導入はそれを見直すよい機会にもなりました。おかげさまで、かなりきれいなデータになりましたよ。
-データの移行開始から公開まで、実際の期間はどれくらいでしたか?
小林さん:移行開始が2023年の6月、公開は2024年3月ですから、9か月ほどですね。その後、2024年度から現場での運用がスタートしました。
-すごいスピード感です。事前の準備の賜物ですね。では、システムをお使いになってのご感想は?
小林さん:独特のクセのようなものを感じて「慣れが必要かな」と思っていましたが、割とすぐに慣れました。それに、最近インターフェイスのリニューアルがありましたが、ずいぶん見やすくなりましたよね。
-ありがとうございます。逆に気になることはありませんか?
小林さん:「クリップリストを並べ替えたいな」と思うことは、よくありますね。常設展のプランを検討する時によく使うんですが、テーマと順番が大切になりますので。
-申し訳ございません、実は他館の方からもご要望をいただいておりまして。システムの仕組み上、大きな改修が必要なので、しばしお時間をいただければと思います。
小林さん:ぜひお願いします。
-かしこまりました(メモ)。ちなみに、常設展のご準備で資料利用の機能をお使いであれば、対象資料一覧の並べ替えはできますよ。
小林さん:できれば画像が見えている状態で並べ替えたいんです。展示順を検討する時、学芸員によっては画面をそのまま出力して、ハサミで切って並べながら考えていますから(笑)。
-うわ~、そんなにご面倒をおかけしているのですか! そのご苦労を社内で共有して、スピードアップに努めます(メモ)。
小林さん:恐れ入ります(笑)。
-ところで、巡回展についてはどう管理されていますか? 巡回先ごとに個別の展覧会として扱うか、それとも最初から最後までをひとまとめで扱うか。
小林さん:後者ですね。1館目の情報を詳しく記述して、2館目以降の特筆事項は備考欄に記載しています。当館にとって最も重要な情報は、作品の展示日数となりますから。
-なるほど、勉強になります(メモ)。
 -さて、それでは今後の展望などをお聞かせください。
-さて、それでは今後の展望などをお聞かせください。
小林さん:まずは画像データを充実させたいですね。サムネイルだけでは寂しいので、高精細な画像を公開したいと考えています。
-著作権へのご対応はいかがですか?
小林さん:当館のコレクションは近現代のものが多いので、全体の3分の2くらいが著作権の保護期間内にある作品なのですが、ここまでお願いした方々からは概ねご許可をいただけていますね。作家さんご本人からご遺族までいろいろなケースがありますが、丁寧に対処しています。
-それだけで大変なお仕事ですよね。作品解説などの整備はいかがですか?
小林さん:2024年度に、100点ほどを対象に一般の方向けの解説を増やしました。これまでに発行したニュースレターなどに掲載していたものを登録したり。
-公開に留まらず、情報の充実にも積極的ですね。
小林さん:そうですね。たとえば、小中学校の先生方への情報提供など、データベースは地域連携の事業にも役立ちそうですし。I.B.MUSEUM SaaSには二つ目の公開ページの機能がありますから、どう活用しようかなと今からワクワクしているんですよ(笑)。
-子ども向けに特化したり、ダウンロード可能な作品のページにしたり、他館でもさまざまな形でご活用いただいておりますので、よろしければ事例をご紹介しますね。そのほかに、何かご要望などはございますか?
小林さん:作品の状態を手書きで記入できる機能があったらいいなと思います。画像に直接書き込むようなイメージで。
-なるほど、それはいいですね。研究してみます(メモ)。
小林さん:あとは、今後はジャパンサーチも活用していきたいのですが、現在データを提供中のアートプラットフォームにも連携機能が欲しいですね。
 -こちらも検討します。本日はたくさんのヒントをいただき、お話をうかがった甲斐がありました。お忙しいところ、本当にありがとうございました。
-こちらも検討します。本日はたくさんのヒントをいただき、お話をうかがった甲斐がありました。お忙しいところ、本当にありがとうございました。
- Museum Profile
-
府中市美術館
緑豊かな府中の森公園の中、静かな環境で芸術を楽しめる美術館です。日本の近現代の絵画を中心に、個性的な企画展も多数開催中。建物は自然光を取り入れた開放的な設計で、ゆったりとした時間を過ごせます。館内のカフェでは展覧会にちなんだメニューを味わうことができ、ミュージアムショップではオリジナルグッズも充実。地域とのつながりを大切にしながら、誰もが気軽にアートに触れられる場所として親しまれている人気施設です。
〒183-0001 東京都府中市浅間町1丁目3番地(都立府中の森公園内)
電話番号:042-336-3371(代表)
ホームページ:https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/