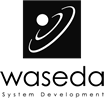- vol.224取材年月:2025年7月豊見城市歴史民俗資料展示室
バーチャルなデータであっても、記憶と想いを乗せれば
人々の心を動かす「活きた情報」として提供できる。班長 / 学芸員 島袋 幸司 さん
主事 / 学芸員 奥原 三樹 さん
 -I.B.MUSEUM SaaSのご導入からすでに情報公開も実現されて、デジタルアーカイブ事業は順風満帆ですね。まずは導入以前のご様子からお聞かせください。
-I.B.MUSEUM SaaSのご導入からすでに情報公開も実現されて、デジタルアーカイブ事業は順風満帆ですね。まずは導入以前のご様子からお聞かせください。
島袋さん:平成22〜23年にデジタル化事業が始まり、内部用のデータベースを構築しました。平成27年にフィルム収集事業が始まり、公民館での上映や展示を行っていたのですが、もう少し利活用を進めようということでデジタルアーカイブの公開と写真集の発刊を実施することになったんです。
-外部公開へと軸足が移ってきたわけですね。その当時は、以前のシステムを内部用として併用されていたのですか。
島袋さん:それが、OSのアップデートで動かなくなりまして。以前の担当者が取っておいてくれた御社の資料で検討して、令和元年に導入しました。
-デジタル博物館事業については。
島袋さん:導入翌年から開始した事業で、収蔵品だけでなく文化財や館の資料、市史編さんに関わる資料などを調査して整理・公開しています。
-データの幅が広くて、一人で対応できる量ではありませんよね。
島袋さん:ええ、会計年度任用職員を含めて5名の体制で取り組んでいるのですが、写真資料の公開についてはまだまだですね。ただ、調査としては豊見城48の自治会のうち34まで完了しています。
-順調ですね。写真資料は、各時代を網羅しているのですか?
島袋さん: 戦前は沖縄戦で大半が焼失していてすごく少数ですね。戦後でも1960年代の台風で浸水被害があった地域は、やはり流失してしまったのか、数が少ないですね。将来起こり得る災害に備える意味でも、デジタルアーカイブの意義を実感しています。
-まさに地域の財産を守る事業、頭が下がる思いです。
 -公開側の「とみぐすくデジタルアーカイブ」のトップページは、島袋さんご自身で構築されたと伺いました。
-公開側の「とみぐすくデジタルアーカイブ」のトップページは、島袋さんご自身で構築されたと伺いました。
島袋さん:はい、まだ試験的な段階ということで、Googleのサービスで作ったページからI.B.MUSEUM SaaSの公開ページにリンクさせています。制作では、天城町さんのサイトを参考にさせていただいたんですよ。
-そう言えば、天城町様も専門業者に委託せずに作っておられますよね。今後、データが充実してきたら、南城市様のようなWeb APIを活用したサイトも作れそうです。
島袋さん:I.B.MUSEUM SaaSの公開ページでは、項目をそのままリンクにできますよね。地域名をクリックすると同じ地域の文化財の写真などを次々と見てもらえる形にしたいのですが、Web APIではこの動きを作るのが難しそうで。
-確かに、項目から作成したリンクがたくさんありますね(サイトを見ながら)。
島袋さん:はい。ただ、リンクにできない項目もあるようで、その区別がよく分からないんです。
-なるほど。具体的な操作については、改めてサポート担当から説明させていただきますね(メモ)。
島袋さん:ぜひお願いします。それと要望があるのですが、よろしいですか?
-もちろんです、何でもお聞かせください。
島袋さん:複数のデータを修正する際は、編集してアップロードするためにまずExcelに出力しますよね。この時、Excel上に必ず残しておかなければならない項目がもう少し分かりやすく表示されていると助かります。
-一括更新に必要な項目と、そうではない項目をExcel上で判別したいわけですね。確かに、その方が分かりやすいかもしれません。これは社に持ち帰って検討課題とさせていただきます(メモ)。
島袋さん:それから、メディアをフリーワードで検索できるようになると便利かなと思います。ひとつの画像をほかでも使いたいケースは割と多いので。
-写真というジャンルで登録しているけれど、文化財の資料でもある…といったケースでしょうか。確かに、サッと探すにはフリーワード検索の方が適していますね。こちらも社内で議論いたします(メモ)。新しいインターフェイスについてはいかがですか?
島袋さん:あ、とても使いやすいと思いますよ。特に一括登録ではアップデート中であることが分かりやすくなって、とても助かっています。
-それはよかったです。疑問などが生じたらご連絡くださいね。
 -さて、システムの話題とは少し離れますが、「平和学習VR」が報道を賑わせましたね。
-さて、システムの話題とは少し離れますが、「平和学習VR」が報道を賑わせましたね。
島袋さん:お陰様で、たくさん取り上げていただきまして。当VRのベースには「とみぐすくタイムマシン」が使用されています。大正~戦後の地図を3Dで再現したコンテンツで、1947年に米軍が作成した地形図と戦前の航空写真を貼り合わせて3D化したんです。そこに戦前の集落を3Dで復元しています。
-(画面を見ながら)かなり細かく再現されていますよね。でも、地図や航空写真では、ここまでの情報は読み取れませんよね?
奥原さん:そこは、数年かけて聞き取り調査を実施したんです。
-それはすごい、貴重な証言を分かりやすい形でコンテンツに組み込んだわけですね。
奥原さん:そうなんです。たくさんの方々に話を聞かせていただいて、屋根や石垣の様子とか、「当時はここに水槽があって、亀を飼っていたんだよ」とか、ひとつひとつの細かい情報を反映しているんですよ。
-う〜む、最先端のデジタル技術の裏には地道な作業の積み重ねがあるのですね…。
奥原さん:そこで暮らした方々の想い出やエピソードを乗せていくことで、データに説得力を持たせられますからね。3D空間ですが、「活きた集落」に迫ることができたと思います。
-いや、とても勉強になります(メモ)。
島袋さん:アナログのジオラマを作成する時にも、同じような手法を使うことがありますからね。
-なるほど、VRはデジタルのジオラマですね。解説のほか、当時の写真や3Dデータが表示されているので、I.B.MUSEUM SaaSと連携でコンテンツを増やしていけそうです。たとえば、家の中に3Dの民具が置くとか。
島袋さん:それは面白いですね! 民具や文化財の3Dデータ作成も進めているので、元の環境に配置するのも良さそうですね。試してみようかな。
-え、3Dデータまで自作できるのですか!
奥原さん:本当にすごいですよね。後任としてプレッシャーを感じます(笑)。
-写真や3Dなど興味を刺激するコンテンツを入り口で強調すれば、さらに魅力づけできそうですね。
島袋さん:その意味でも、現在のようにシステムを軸にして自由に組み立てていく手法が合っていると思うんです。そうそう、登録した写真をAIに認識させて、適したタグを付けていくというフローを構築することは可能でしょうか。
-生成AIの組み込みに関しては、まさに研究しようと考えているところです。少しお時間をください(メモ)。
島袋さん:それから、ご覧になった方々に写真などの情報をお寄せいただけるような仕組みを作りたいですね。双方向のコミュニケーションが淀みなく流れるようになれば、デジタルアーカイブとしてどんどん活発化していくと思いますので。
-他の自治体でそうした取り組みも出始めていますので、調べた上で改めて報告させていただきますね。本日はとても勉強になりました。ご多忙の中、本当にありがとうございました。
- Museum Profile
-
豊見城市歴史民俗資料展示室
2002年、沖縄県豊見城市の中央部にある豊見城市立中央図書館1階に開館した、入館無料の資料館です。市指定文化財や出土遺物をはじめ、農具や戦後復興期から復帰前後の生活用品、祭礼や行事に使われた道具類など多彩な展示に、往時の暮らしを伝える茅葺き民家まで再現。収蔵品を検索できるデジタルアーカイブからYouTubeチャンネルまでデジタル活用にも積極的で、子どもから大人まで幅広い学びのニーズに応える地域の重要な学習拠点です。
〒901-0232
沖縄県豊見城市伊良波392番地
電話番号:098-856-3671
ホームページ:https://www.city.tomigusuku.lg.jp/soshiki/8/1035/gyomuannai/3/4/326.html