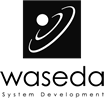- vol.222取材年月:2025年6月郡山市歴史情報博物館
デジタルアーカイブの構築経験がある外部の力を借りて
開館と同時に公開まで実現することができました。館長 嶋根 裕一 さん
学芸員(主査) 渡邉 裕太 さん
学芸員(主査) 國分 梓 さん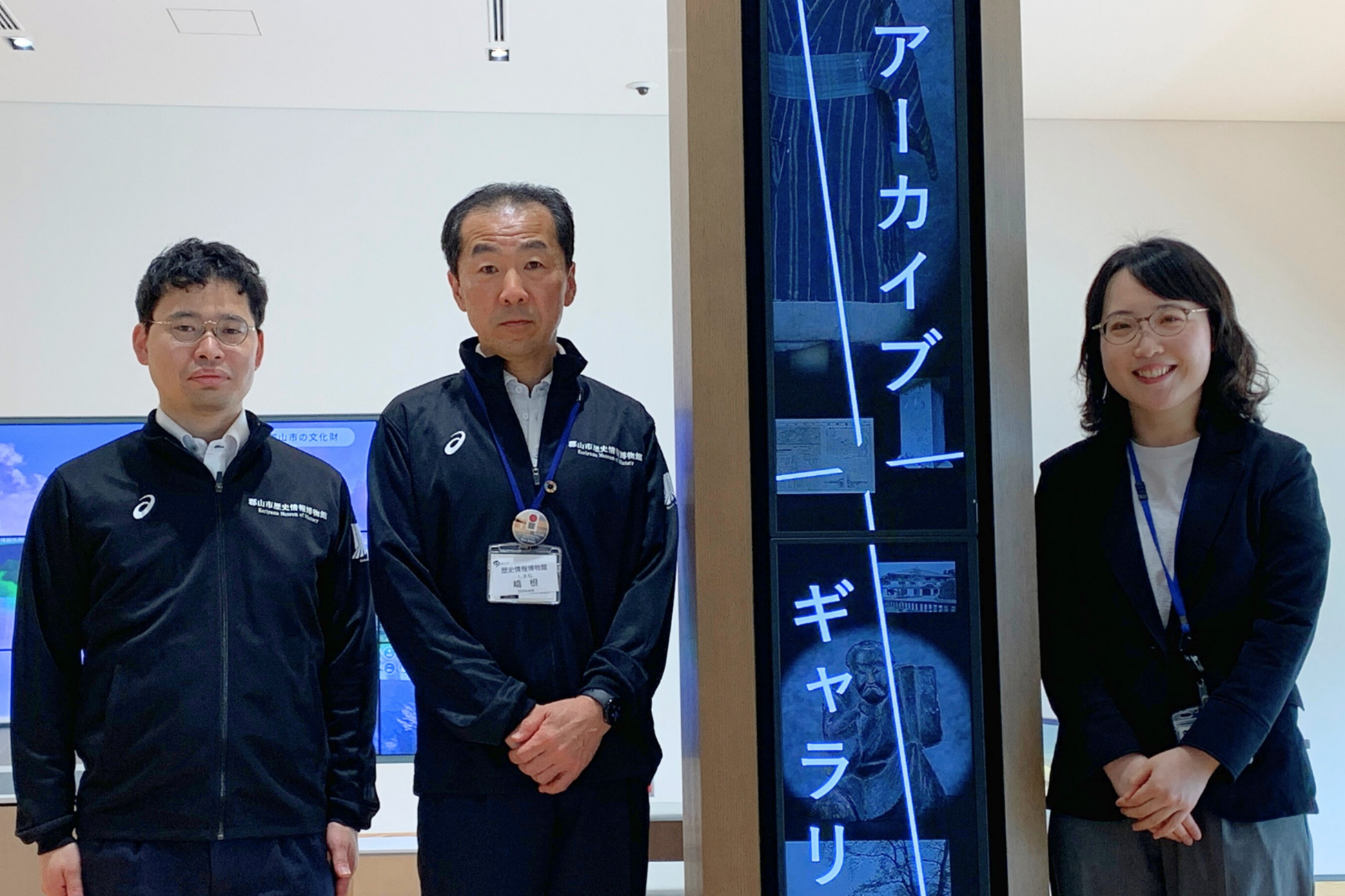
 -科学やデジタル技術がテーマではない博物館で名称に「情報」と入るケースは、国内でもかなり珍しいのではないかと思います。何か特別な理由がおありなのでしょうか。
-科学やデジタル技術がテーマではない博物館で名称に「情報」と入るケースは、国内でもかなり珍しいのではないかと思います。何か特別な理由がおありなのでしょうか。
嶋根さん:当館は、もともと(仮称)歴史情報・公文書館として整備を進めてきましたので、その影響ですね。
-なるほど。サイトには「公文書館機能を有する」とありましたが、もとの構想が公文書館だったのですね。
嶋根さん:そうなんです。最終的には博物館の機能、市民の交流拠点の機能も加味されましたが、3つの柱として公文書館の機能もしっかり守っていますので、「情報」という2文字に込めた…といった感じでしょうか。
-開館時にデジタルアーカイブの公開まで実現されたのは、まさに「情報」という言葉を冠したミュージアムに相応しいと思います。開館準備でご多忙な中では、相当に大変な作業になったのでは。
國分さん:「デジタルアーカイブは何としても公開しないと」と考えていましたので、正直なところプレッシャーはありました。とにかくきちんと整備して開館を迎えようという一心でした。
嶋根さん:本当に、みんなの頑張りの賜物です。
-2021年にI.B.MUSEUM SaaSを導入いただいて今年3月の開館ですから、4年間で整備された計算になりますね。当時はどんなご様子だったのですか?
國分さん:私が着任した頃は、すでに導入は決まっていて運用開始を待っている状態でした。私が担当する歴史分野は約9万点の資料があり、そのうち目録化されているものが約6万点ありました。
-うわ〜、すべて紙からのスタートだったのですね…。
國分さん:民俗分野はExcelデータがありましたね。あとは、考古分野は調査報告書がベースで、公文書については一部がマイクロフィルムで保存されていて件名目録のみデジタルデータがある状態でした。
-その状態から、開館準備をこなしながらひとつのデータベースに情報を統合し、デジタルアーカイブの公開まで到達されたことに改めて驚きます。「これは無理かも」とは思いませんでしたか?
國分さん:はい、さすがに「どうしよう?」とはなりました(笑)。
-それでも乗り越えられた秘訣は?
國分さん:デジタルアーカイブ構築のサポート経験をお持ちの業者さんにメタデータの作成から委託できたことが大きいと思います。3万点を2年かけて登録するペースで、私たちは主にチェック作業を担当しました。
-いま検索したら、すでに10万点以上公開されていますね。チェック作業だけでも気が遠くなりそうです…。
嶋根さん:あとは、一部の資料については撮影も。
-え、撮影まで? 開館準備の時期は、建築や展示関係だけでも忙殺されるのに…。
國分さん:大型の資料など専門的な技術が必要な撮影はプロにお任せしましたが、自分たちでできそうなものはできる範囲で撮影しました。
-画像も部門によって管理方法が異なっていたのですか?
國分さん:はい、たとえば考古分野は文化財調査研究センターが撮影した写真がありました。歴史分野では昭和50年代に作成したマイクロフィルムを保管していましたので、そのデジタル化もこの時期に進めたんです。
-いや、本当によくぞここまで漕ぎ着けられました。素晴らしいです。
-さて、公開ページの「郡山コレクション」はI.B.MUSEUM SaaSのWeb APIをお使いいただいていますね。とても見やすくて魅力的なページに仕上がっていると思います。
國分さん:ありがとうございます。検索キーワードが思い浮かばない方も多いと思いますので、たくさんの画像を並べてワンクリックで詳しい情報にアクセスできるようにしたんです。画像はリロードのたびに入れ替わる仕組みになっています。
-ただ、先ほどのお話をうかがうと、各分野の交通整理が大変そうです。
國分さん:実際に大変でした。項目体系も項目名も違いますし、そもそもリストの状態からしてバラバラでしたからね。サポートしてくださった業者さんがデジタルアーカイブの知識をお持ちだったので、本当に助かりました。
渡邉さん:展示室でもさまざまな方法でデジタルを活用しているのですが、そこでもシステムから取得したデータを活用しているんですよ。
-あ、受付の近くでいくつか拝見しました。3Dコンテンツを楽しめるタッチモニターと鳥瞰図に情報が表示される大型モニターとか、タイプの違うデジタル展示に合わせたデータの使い分けが上手だなと感心したのですが、展示室内でも展開しておられるのですね。
渡邉さん:はい、展示室ごとに発信方法を工夫していますので、ぜひご覧ください。
-ありがとうございます。では、この後に。ところで、ホームページには収蔵品のデータベースのほかに「こおりやまアーカイブ」というコンテンツがありますね。
渡邉さん:あれは、市民の皆様から資料を提供していただく枠組みなんです。まだ始まったばかりで、お寄せいただいたものはまた別のデータベースにストックして公開していく予定なんですよ。
-なるほど、市民参加型のプロジェクトは館のコンセプトの「交流」とも繋がりますね。
 -I.B.MUSEUM SaaSをお使いの中で、何か気になることはありますか?
-I.B.MUSEUM SaaSをお使いの中で、何か気になることはありますか?
國分さん:今もコツコツとデータを追加しながら公開しているのですが、画像の登録日の情報はWeb APIで出せないようですね。新規に登録した画像をWeb APIで識別できると、新着情報が分かりやすくなると思うのですが。
-申し訳ございません、改善課題とさせていただきます(メモ)。クリップリストや帳票作成など管理用の機能についてはいかがですか?
渡邉さん:まだ利用していないんです。操作方法はご説明いただきましたので、今後検討して参りたいと思います。
-開館間もない時期は、データベースまわりのお仕事は登録と公開に集中しますよね、大変失礼しました。これらの機能は日常業務の効率化に直結しますので、よろしければ落ち着いたところで改めて操作説明会を開催しますよ。
渡邉さん:ありがたいです、ぜひお願いします。
-承りました(メモ)。では、最後に今後の展望などを。
國分さん:この後は、まずはジャパンサーチとの連携ですかね。当館だけで決められることではありませんが、個人的には将来は市の各部署と協力して情報発信できたらと思っています。
嶋根さん:市の他部署でもI.B.MUSEUM SaaSを利用していますしね。
-なるほど、連携体制は構築しやすそうです。
國分さん:検索ページのタイトルも「こおりやまコレクション」としましたが、これからは市内の文化施設の中核的な役割を担うことになりますので、さまざまなスタイルで情報を発信していきたいですね。
-夢が広がりますね。弊社も可能な限りサポートさせていただきます。本日はお忙しい中、ありがとうございました。
- Museum Profile
-
郡山市歴史情報博物館
令和7年3月に開館した、博物館機能と公文書館機能を併せ持つ東北初の複合施設です。郡山市の歴史・民俗・考古などの資料を幅広く収集・展示しており、展示室では随所に最新のデジタル技術を活用するなど、驚きと発見に満ちたミュージアム体験を提供。歴史的公文書の保存・活用のほか、ワークショップなどイベントの開催や交流スペースの提供など、市民の「調べたい」「学びたい」というニーズに応える注目の「知の結節点」です。
〒963-8876 福島県郡山市麓山一丁目5番30号
Tel:024-923-8921
ホームページ https://www.city.koriyama.lg.jp/site/historymuseum/